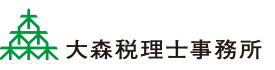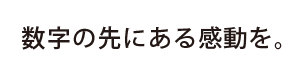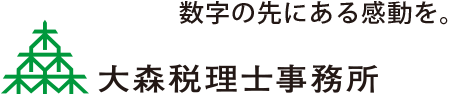<一時所得の計算方法>
個人の所得税を計算する際には、所得の形態に応じて所得の種類を『事業所得』や『不動産所得』、『給与所得』といった形で細かく分類します。
その中に『一時所得』という種類があります。
この『一時所得』の計算方法は、下記のとおりです。
(総収入金額-その収入を得るために支出した金額-50万円)×1/2
<『支出した金額』とは?>
では、上記の計算式にある『その収入を得るために支出した金額』とは、どのような支出を指すのでしょうか?
この『その収入を得るために支出した金額』とは、文字どおりその収入を得る為に要した原価としての性質を有する支出を指します。
具体的にみてみましょう。
この一時所得の代表例として『生命保険の返戻金』があります。
例えば、養老保険を契約し、当初は契約者を法人であるA社としておき、保険契約期間の途中でその契約者の地位をA法人の代表者である個人甲に変更したとします。
契約者がA社である期間中は、A社が支払った保険料(1,000万円)を損金に計上していたとします。
その後、契約者を個人甲へ変更し、個人甲が保険料を1,000万円支払ったとします。
そして当該生命保険を解約し、解約返戻金として3,000万円を受け取ったとします。
この場合、個人甲の一時所得の計算上、総収入金額(3,000万円)から控除することが出来る『その収入を得るために支出した金額』は、幾らになるのでしょうか?
答えは『個人甲が支払った1,000万円のみ』です。
言われてみれば当然のように思いますが、昔は、A社が支払っていた保険料(1,000万円)と個人甲が支払っていた保険料(1,000万円)との合計額である2,000万円を『その収入を得るために支出した金額』として総収入金額(3,000万円)から控除する、という節税手段が横行していたのです。
現在では、この点の取扱いが通達上で整理され『その収入を得るために支出した金額』として控除出来る金額は、『満期返戻金等の支払いを受ける者が自ら支出した保険料』に限る旨が明記されています(所基通34-4)
≪終わり≫