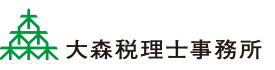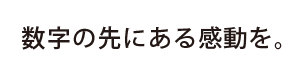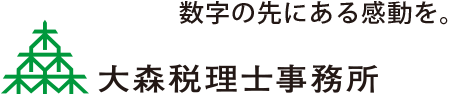<オーナー社長から土地を借りる>
オーナー社長が所有している土地を借り受けて、当該土地の上に賃貸マンションを建築して不動産賃貸業を営む同族会社は多いと思います。
このオーナー社長から土地を賃借する際ですが、その地域が土地の賃貸借をする際に権利金等の授受をする慣習のある地域である場合、具体的にいうと国税庁が公表している路線価図に『借地権割合』が付されている地域であれば、原則として土地を賃借する際に権利金を支払う必要があります。
もし、権利金を支払わず、且つ、相当の地代の支払いが無い場合には、オーナー社長から同族会社への借地権の贈与があったものとみなして、同族会社側に借地権の受贈益が発生してしまいます。
では、同族会社側に権利金を支払うだけの資金力が無い場合には、どうすれば良いのでしょうか?
<無償返還届出書を提出する>
このような場合には、税務署に対し貸主と借主との連名により作成した『土地の無償返還に関する届出書』という書類を提出すれば、権利金の支払いをしなくても同族会社側に借地権の受贈益が発生することを回避出来ます。
何故か?というと、当該届出書は、『将来において、借主は賃借している土地を無償にて貸主へ返還しますよ』という意味を持っています。
つまり、『借主は、当該賃借している土地に対しては借地権を有していません』という旨を宣言することになります。
よって、借主側である同族会社には借地権が存在しないことになる為、借地権の受贈益も発生しない、という訳です。
<土地の相続税評価額は△20%減となる>
上記のとおり、土地の無償返還に関する届出書を提出すると同族会社側には借地権は存在しないことになります。
とは言え、同族会社が当該土地の上に賃貸マンション等の建物を建築して使用収益している以上、当該土地の利用価値はある程度制限されることになります。
つまり、『不便になる』という訳です。
よって、当該土地の相続税評価額を算定する際には、この『不便になる』という要素を加味し、当該土地の自用地としての評価額から△20%分を減額することとしています。
<減額した分は同族会社の株式評価額に加算する>
上記のとおり、当該土地の相続税評価額からは、△20%分が減額されます。
これだけを見ると『お得感』がありますが、世の中そう美味い話だけではありません。
ここで減額された△20%分の評価額は、当該土地の借主である同族会社の株価を算定する際、当該同族会社の純資産額に加算することとなっているのです。
つまり、その加算された分だけ同族会社の株価が上昇する訳です。
という事は、オーナー社長が同族会社の株式を100%所有していると、土地の評価額からは△20%分が減額されるものの、その一方で、所有している同族会社の株価が+20%上昇するので、オーナー社長全体の財産評価額自体はプラスマイナスゼロとなります。
<ではどうするか?>
では、どうすれば、『土地の評価額から△20%を減額出来る』という減額効果を最大限に享受出来るのでしょうか?
その為には、上述した『土地の無償返還に関する届出書』を提出する前(=同族会社との間で土地の賃貸借契約を締結する前)にオーナー社長が所有している同族会社の株式を後継者へ移転させることが必要です。
後継者に株式を移転させる方法としては、下記の方法があります。
①後継者に贈与する
受贈者である後継者に贈与税が課される為、後継者に納税負担が発生します。
②後継者に譲渡する
譲渡者であるオーナー社長に譲渡所得が発生する為、オーナー社長側に納税負担が発生します。
但し、株式の譲渡所得に対する税率は、売却益がどんなに多額になっても20.315%(所得税+復興特別所得税+個人住民税)で済むという利点があります。
③事業承継税制を適用する
細々とした要件を満たす必要がありますが、贈与税の負担無しで後継者へ株式を移転出来る利点があります。
④相続時精算課税を適用する
一定の限度額までは非課税で後継者へ株式を贈与出来ます。
仮に限度額を超過して贈与税が発生したとしても、その税率を20%に抑えることが出来ます。
上記の方法によりオーナー社長から後継者へ株式を移転すれば、土地の相続税評価額から△20%減額された分が同族会社の株価に加算されても既にオーナー社長の手元には同族会社の株式は無い訳ですから、オーナー社長の財産から△20%減額するという減額効果を最大限に享受出来ることになります。
≪終わり≫